発音のために遊びや食事でできること
前回の“構音(発音)”に続いて
今回は“構音改善に向けて、遊びや食事でできること”についてです。

普段から、何気なくおしゃべりしている私たちですが
一つ一つの音を発音するために 口を開ける時の 大きさや形、
舌の位置など 微妙な違いで 音を使い分けて発音しています。
そういった、発音に必要な口の動きは赤ちゃんから学習が始まっています。
生後2ヶ月くらいの赤ちゃんは、「アー」や「ウクー」など
お母さんの口元の動きにこたえようと、声を出したり、
口を一生懸命に動かしてくれます。
![]()
しばらくすると、「アブー」「ババババ」など色々な声を活発に出すようになり
口や舌の動かし方や、声の調節を学んでいくのです。
また、その時期から離乳も始まってきます。
口や舌は食べる器官でもあるので、大人の食べ方を練習していく過程でも、
発音に必要となってくる様々な動きを
少しずつ・ゆっくりと勉強していくのです。
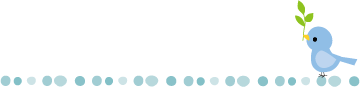
お食事のように、日々の生活の中でお口や舌を使うことは
話すこと以外にもたくさんあります。
・「吐く」
・「吸う」
・「噛む」
・「うがい」
・「鼻かみ」など…
これらは、発音にも必要になってくる大切な運動です。
お口や舌の動かし方を意識できるような関わりが
正しい発音への近道になるかもしれません。
今回は、そういった発音に必要になってくるお口の運動に着目して
楽しく発音のためにできることを何点か、ご紹介したいと思います。
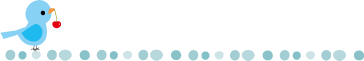
<?真似っこあそび?>
お子様が自分の口や舌の動きに注目をすることは
とても難しいことです。
「お口を開けたまま、舌を出して・・・」なんて
頭で考えたことを、実際に動かしてみることは難しいものですよね。
『相手の動きを真似っこする』ことは
自分の身体の動かし方に注目する大切なことの一つです。
お顔の舌やお口の一部分の動きに注目することは
とても難しいことでもあります。
まずは、大きな体の動きのものまねから始めてみると良いかもしれません。
動物になりきって、様々な身体の動かし方を経験してみたり、
手遊び歌で楽しく、手を動かしてみたりすることも
発音に繋がる大切な関わりの1つです。
ある程度、月齢の高いお子様には、 “あっぷっぷ”や“あっかんべー”など
顔の動きを、真似っこしてみるのもいいかもしれませんね。
<?口の動き?>
息を吹く。ただそれだけのことですが
「フ――」と、ゆっくり・やさしく吹く
「フッ」と早く・強く吹く
唇の開け具合の調節や、吐く息のスピードの調節が必要です。
『シャボン玉』や『笛』でゆっくり・やさしく
『ラッパ』や『風車』で早く・強く
色々な強さや速さの息を吹いて、
唇の動きの調節を、たくさん経験していけると良いでしょう。
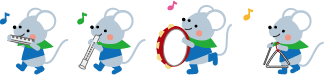
<?舌の動き?>
舌の動きは、発音の時も重要ですが、食べる時もとても重要になってきます。
飴をすぐにかんでしまう、ガムをすぐに吐き出してしまうことがあれば、
舌を口の中で自由に動かすことに苦手さがあるかもしれません。
棒付きのぺロぺロキャンディなどで、美味しくなめながら
舌を動かす練習をしていけると良いかもしれません。
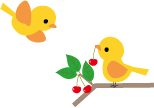
今回は、発音へ繋がる遊びや関わり方を、少し紹介させていただきました。
今回ご紹介できなかったことも含めどれも共通していることは
『大好きなお母さんやお父さんと じっくりとやり取りを楽しむこと』です。
きっと、発音の成長にとっても、
それが、大切なことなのかもしれませんね。
参考文献:「4歳までのことばを育てる 語りかけ育児」 中川信子著 PHPエディターズ・グループ
おすすめ記事はこちら


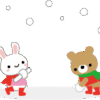


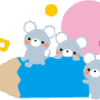
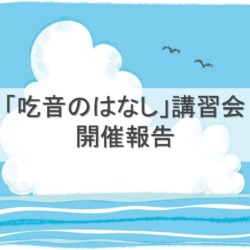









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません