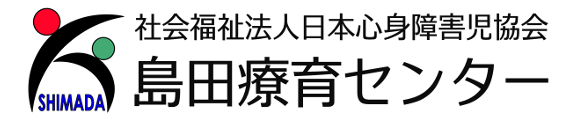療育の内容に応じて、各専門職が対応いたします
当センターでは、医師・療法士の診断・評価を元に策定したリハビリテーション計画に基づいて、各種リハビリと相談事業を実施しております。約50人のリハビリテーションスタッフが皆様の療育をサポートします。

理学療法(PT)、作業療法(OT)、言語聴覚療法(ST)、心理検査・相談の受け入れに関して
1.リハビリの利用に関して
評価・検査(以下評価)、各種訓練・相談(以下訓練)ともに医師の判断・指⽰のもとに実施されます。また、評価・訓練開始後も3か⽉毎の診察 が必要です。
OT訓練は年少からの開始となります。また、OT・STの定期訓練は原則として就学前までとさせていただいております。
2.他施設利用の方の評価・訓練について
近年、児童福祉法に基づき、障害者福祉サービス受給者証を利⽤して児童発達⽀援(療育)を提供する 機関(児童発達⽀援センター、児童発達⽀援事業所)が整備されてきたため、改めて当センターのリハ ビリテーション部⾨への受け⼊れルールを再構築いたしました。
(1) 評価は実施しております。
(2) 定期訓練は評価結果を踏まえて主治医が実施を検討いたしますが、他施設にてサービスを受けている方への訓練は行わない場合がございます。下記内容をご確認ください。
| 病院、医療型児童発達⽀援などで個別訓練・指導 を受けている⽅ |
同職種での訓練は行いません 例)他施設でOTの個別訓練を受けている方は当センターでOTの個別訓練は受けられない 等 |
|---|---|
| 受給者証で旧通園施設または同等の通所施設や、児童発達支援を利⽤されている方 (例:すぎな愛育園、町⽥市⼦ども発達センター、ひまわり教室、幼稚園・保育園に併設された支援サービス、放課後デイサービスなど) |
評価の上検討 |
ご不明な点はお問い合わせください。
リハビリテーション各科のご紹介
その他のリハビリテーションサービス
病棟、外来、通所の利用者様を対象に理学療法訓練を行っています。身体所見の評価を行い、姿勢や運動を改善するため運動療法、運動発達の遅れに対して運動発達の促し、呼吸機能の問題に対して呼吸療法を行っています。通院が難しい利用者様には訪問リハを行っています。また、障害児者が日常生活をより過ごしやすくするため車椅子、座位保持装置、補装具等のアドバイスも医師と一緒に行っています。

<対象>
- 医療ケアが高い超・準超重症児者
- 脳性麻痺・二分脊椎・染色体異常・筋疾患等の肢体不自由児者
- 運動発達の遅れ
理学療法訓練の様子
遊びなどの活動を通して心身の発達を支援します。利用者様の基本的な動作能力や、社会適応する能力を獲得するため、様々な作業活動を通して「その人らしい生活」を支援していきます。当センターでは、食事や着替えなどの生活動作や、姿勢を含めた運動や手先の細かな操作につまづきがあるお子さんに対して、主に遊びを通して発達を支援していきます。また、遊びの中で見る・聴く・触るなどの感覚を養う活動を行い、お子さんが“やってみたい!”とチャレンジする気持ちを育てます。

<対象>
- 脳性麻痺・二分脊椎・染色体異常・筋疾患等の肢体不自由児者
- 発達の遅れ
- 食具や書字など、道具操作の困難さ
- 運動の苦手さや姿勢の崩れやすさ
作業療法訓練の様子
病棟、外来、通所の利用者様を対象として言語聴覚療法の評価・訓練を実施しています。主治医の指示のもと、聴覚(きこえ)、言語(ことば)・コミュニケーション、摂食・嚥下機能(食べること・飲み込むこと)に関する評価・検査を実施し、発達に合わせた言語・コミュニケーション、摂食・嚥下機能に関する訓練・フォローを実施しています。

<対象>
- 知的発達の遅れ
- 言語・コミュニケーションの発達の遅れ
- 読み書きに関する困難さ
- 発音の誤り
- 吃音
- 摂食・嚥下機能に関する困難さ、および発達の遅れ
言語聴覚療法訓練の様子
病棟、外来、通所の利用者様を対象に、心理・発達評価、心理相談を実施しています。発達の状況や心の状態について、心理検査や行動観察、情報収集に基づき評価を行い、個々の状況に応じた支援の提供を行っています。支援内容は、利用者様のニーズやライフステージに応じ、発達の支援や社会的スキルの指導(SST)、不適切行動の軽減、学習支援、生活支援等多岐に渡ります。
ご本人だけでなく、保護者の方、地域の方々(幼稚園・保育園や小中学校、学童等)に対して、以下に挙げたような事項について、ご相談をお受けしています。

- 発達全般
- 心の状態
- コミュニケーション
- 気持ちや行動のコントロール
- 集団参加
- 不登校支援
(ページ下部の『たまる~む』もご参照ください) - 対人関係(友人、家族等)
- 学習のつまずき
- 眼球運動・視覚認知
- 余暇支援 等
心理指導の様子
その他のリハビリテーションサービス
「親子で楽しみ」「励まし合い」「少し勉強をして」大きな集団に入るまでのステップに。多摩市から助成金をいただき、活動をしています。
グループの目的

- 遊びの中で人とかかわる力や感覚・運動の発達を促す
- 食べる力を伸ばす
- 保護者の方の交流の場
指導期間
5月~翌年3月(基本的に第2・4火曜日)
グループ概要
| 対象 | 生後10ヶ月から年少未満までのダウン症のお子さん |
|---|---|
| 時間 | 9時50分~11時頃 |
| 内容 | 親子遊び、感覚運動遊び、摂食相談、 勉強会(コミュニケーション、摂食について) |
| 費用 | 医療保険の適応となっており、実費負担はありません。 |
| 場所 | 島田療育センター デイケアセンター1階 集団訓練室 または 厚生棟研修室 |
| 持ち物 | スプーン、タオル、エプロンなど(おやつ実施日:年3回) |
| 服装 | 親子ともに動きやすい服装 |
| スタッフ | グループ担当医師(医療面をサポートします) 言語聴覚士(ことばや食事についてサポートします) 理学療法士(夏期のプール指導において介助方法をお伝えします) ケースワーカー(参加の相談や運営に関するサポートをします) |
活動の内容
| 集団遊び | 手遊び歌やペープサートなどやりとり遊びを通して、インストラクターやお友だちに注目するなど集団に参加する基盤をつくっていきます。 |
|---|---|
| 感覚運動遊び | 親子で体操や感覚・運動遊びなど体を動かします。 |
| 摂食相談 | おやつの日を設けています。食べることについての心配事や疑問について話し合います。 |
| 勉強会 | コミュニケーション、摂食についての勉強会を年2回行っています。 |
| 交流会 | 毎年夏にほっぺグループの卒業生と現役生合わせての親子交流会を開催し、情報交換などを行っています。 |
ほっぺグループの様子
お申込み
参加前に一度グループの見学をしていただいております。
参加ご希望の方は、支援部 医療相談担当までご連絡ください。
見学後、当センター主治医の指示が必要となります。
グループ当日
受付でファイルを受け取り、問診票で健康チェックをお受けになってからお越しください。
小学校 中・高学年・中学生のための
気軽に、自分のペースで、だれかと一緒に、過ごす場所
たまる~むって?

- 学校にいくのがなんだかしんどい
- 日中、楽しく過ごして、元気を出したい
- 生活リズムを整えたい
- 同じ悩みを持つ人と話してみたい
- 自分のペースで過ごしたい
- でも、誰かと話したい!遊びたい!
そんなみなさんのための 活動の場です。
スタッフが企画する活動(ボードゲーム、制作活動など)のほかに、好きなことをして過ごす自由時間があります。
目的
たまる~むでは、好きなことを楽しむことや、同世代や家族以外の大人との交流を通して、生活リズムを整えながら様々な経験を積み重ね、エネルギーを蓄え、自信をつけることを目的とした活動を実施します。
対象
島田療育センター(多摩)で児童精神科を受診されている小学校中・高学年~中学生の方で次のような方
- 学校に行くことが難しい、あるいは不安である
- 外出の機会が少ない
- 生活リズムが整いにくい
- 気の合う同世代の人や大人との関わりの機会がほしい 等
グループ概要
| 日時・場所 | 毎週火曜日 13:00~14:30 島田療育センター(多摩) |
|---|---|
| 参加費用 | 保険適応 |
| 人数 | 3名から最大10名程度の予定 |
| 持ち物 | 筆記用具、フリータイムで使いたい好みのグッズ、水筒などの水分、など |
| スタッフ | 1~2名の臨床心理科スタッフが、進行やメンバーのサポートをします |
活動内容
| ウォーミングアップ | アンケートに答えて、おしゃべりしたり、クイズをしたりします。 |
|---|---|
| スタッフが企画した活動 | ゲーム:大画面でニンテンドースイッチ/VRゲーム ボードゲーム:人生ゲーム/ウノ 制作活動:スライム作り/バルーンアート など |
| フリータイム | センターにあるものや、持参した本、ゲームなど好きなことをしてのんびり過ごします。大人や友だちとおしゃべりしてもOK。 |
| トーク/アンケート | その日の気分や次回やりたいことなどについて、選択式のアンケートに答えたり、大人や友だちと話したりします。 |
見ているだけ、同じ部屋で好きなことをして過ごす、途中参加、途中退室などもOK。
あなたのペースでご参加ください。
主治医からの指示がありましたら、『たまるーむ』担当者よりお電話でご連絡を差し上げます。
ご本人や他の参加者の状況によっては、ご参加いただけないこともございます。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

発達支援センターセブンクローバーは、発達検査や各種個別相談を医師の診察を経ずにご利用いただけるシステムです。
各種グループ指導や講習会、地域への支援などはセブンクローバーの事業として実施しております。
訪問サービス「ライフケアしまだ」では、現在入院中でこれから医療ケアをともないながら在宅生活へ移られるご予定の方、またそのようなご希望をお持ちの方、ご本人やご家族のご事情により通院が大変でお困りの方などにむけて、訪問サービスを提供しています。今おかかりの医療機関やその他の関係機関と連携しながら、ご本人およびご家族のおすまいでの生活をサポートします。